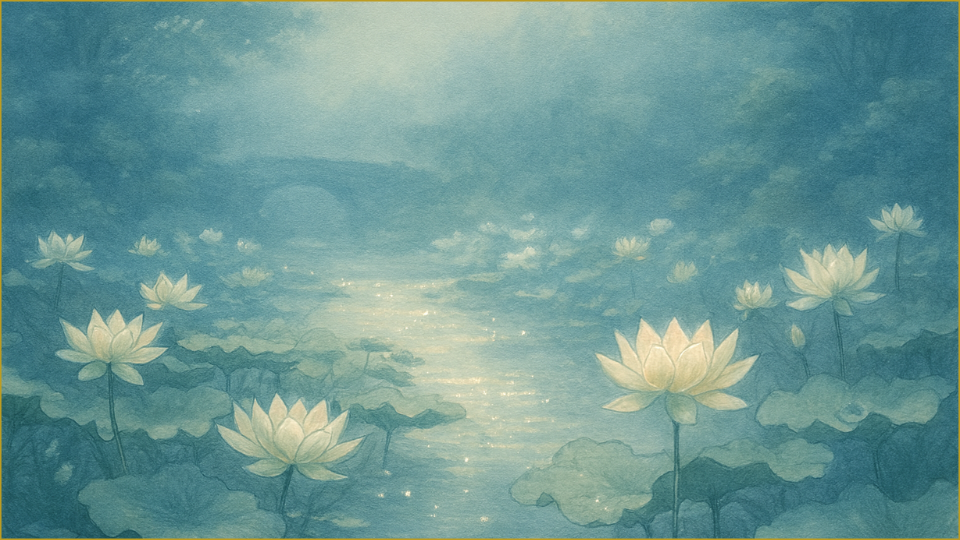癒しを超え、静けさへ。東西の叡智がひらく統合と無為自然の創造
はじめに:東と西、同じ山の頂へ
──「本当の自分」を思い出すための道
東洋と西洋。
二つの文明は、まるで違う言葉と文化をもって、人間という存在の深みに光を当ててきました。
東では、「氣」や「道」という言葉で、宇宙と人がひとつに調和するあり方を探究してきました。
一方、西では「心」や「神」という言葉を通して、人間の内なる世界とその根源的な力を見つめてきました。
──そして、両者が行き着いた先は同じところ。
人はどのような道を歩んでも、結局は不変の真理に到達するのです。
それは、外の世界を変えることではなく、自分の内側に眠る“本当の自分”を思い出す旅路でもあります。
それが、癒しであり、成長であり、目覚めへの道。
東洋の内丹術では、「還虚(かんきょ)」と呼ばれる境地があります。
それは、あらゆる努力や修行を超えて、“無に還る”という、静けさの完成。
一方、西洋心理学の巨人ユングは、人が「自己(Self)」という全体性に目覚めていく過程を「個性化(Individuation)」と名づけました。
どちらも、“自我”という限定的な存在が溶け、“全体”としての自己に還っていくプロセスを示しています。
三和氣功が伝えている「本当の自分を生きる氣功」は、まさにこの二つの道を結ぶ、私たちが自然の流れに「還る道」。
氣を感じ、静けさに身をゆだねるとき、私たちは哲学や心理を超えて、魂が本来のリズムを思い出していきます。
それは、何かを“得る”ための道ではなく、すでに在るものに“還る”ための道。
難しい実践は必要ありません。
このコラムでは、東洋の「還虚」と西洋の「個性化・ヌミノース体験」を照らし合わせながら、三和氣功が指し示す「本当の自分を生きる道」の本質を探っていきます。
内丹術の道:還虚 ― 無に還るという成熟
──「氣」が静けさへと帰るとき
古くから道家の修行者たちは、人の生命は「精・氣・神」という三つの層でできていると伝えてきました。
- 精(せい): 生命の物質的な根源で、身体を構成する基本的な物質。体力・生殖力・成長の基盤で生命の「燃料」となる。
- 氣:生命活動のエネルギー。身体を動かすエネルギー。血液循環、免疫、臓器の働きなどを支える力。精を燃料にして氣が生まれ、体を温め、守り、動かす。
- 神(しん): 精神・意識・魂の働き。思考、感情、知覚、意識などの精神活動。精と氣によって支えられ、心の安定や霊性を司る。
肉体に宿る「精」が洗練されると「氣」となり、氣が澄み渡ると「神(しん)」──つまり意識が清らかに輝き始める。
そして最終的に、その「神」さえも静まり、すべてが“虚(うつろ)”に帰していく。
錬丹とは、このプロセスの内的な実践であり、根源の虚空への帰還の道を、還虚(かんきょ)と呼びます。
「無になる」ことではなく、「本来の在り方に戻る」こと
還虚を、無になることと解釈する人もいます。それは、とても表面的な解釈に過ぎません。
虚に還るとは、“本来の在り方”に還ること。
修行の果てに到達する特別な状態ではなく、私たち一人ひとりの中に、すでに静かに息づいている自然のリズムを知ることなのです。
春に芽吹き、夏に繁り、秋に実り、冬に静まる── 自然のすべてが、活動と静寂の循環を繰り返しています。
人の氣もまた、外へ向かう流れと、内へ還る流れの間を呼吸しています。
還虚とは、その循環の最も深い呼吸。
私たちは、今ここにある自分ではなく、常に外側に起きていることに対して反応するだけの日常を繰り返していますが、
再び自の中心へと戻っていくとき、とらわれすぎていた小さな“私”という輪郭がほどけていきます。
操作から観照へ ― 無為自然という智恵
内丹術の古典では、「還虚」を「守一」「返照」「虚静」とも表現します。
守一(しゅいつ)— 一を守る、一に心を定める
- 意味:「一」とは「道」の根源。そこ心を集中させ、散乱する意識を統一すること。
- 実践:瞑想や呼吸法を通じて、心を一点に定める。雑念を払い、内なる静けさを保つ。
- 目的:心身の統一と、天地自然との一体化。道との合一を目指す。
- 老子曰く:「能守一者、萬物莫之能損」— 一を守る者は、万物に損なわれることがない。
返照(へんしょう)— 内面を照らす、自己を観る
- 意味:外界に向かう意識を内側に返し、自分自身の心を照らすこと。
- 実践:自己観察、夢や感情の内省、瞑想による内的対話。
- 目的:無意識の深層にある「本来の自己」に気づく。魂の浄化と統合。
- 荘子の「心斎」「坐忘」に通じる実践。自我を脱ぎ捨て、魂の本質に触れる。
虚静(きょせい)— 空と静けさに還る
- 意味:「虚(空)」と「静(沈黙)」を極めることで、道と一体化する境地。
- 実践:思考を手放し、自然の流れに身を委ねる。無為自然の中で心を空にする。
- 目的:万物の根源に還ること。痛みや執着を抱えたままでも、静かに「道」に溶けていく。
- 老子第十六章:「致虚極、守静篤」— 虚を極め、静を篤く守る。
それは、意図的に何かを成し遂げようとすることを手放し、意識を“静けさそのもの”へと還る実践です。
氣功の実践では、まず「氣を認識する」段階から「氣を動かす」段階へと進みますが、その先には「氣が自然に流れる」段階があります。
この転換は、実践のゴールであると同時に、人間としての成熟を示すものでもあります。
「こうしなければならない」という緊張がほどけ、「あるがままが働いている」という安心に包まれる。
そこには、無為自然(むいしぜん)──
何もしないのではなく、“すでに完全に調和している生命の働き”への信頼が生まれます。
「氣」を通して感じる無限の静けさ
むずかしい修行をしなくとも、ただ、自分の意識を身体の中心──下丹田に意識を戻すというシンプルな実践で十分です。
氣が静まり、呼吸が穏やかになり、思考のざわめきが遠のくとき、私たちは“在る”という事実そのものに気づきます。
そこでは、何かを治す必要も、何者かになろうとする必要もありません。
ただ、氣が流れ、世界が呼吸している。
その流れとリズムの一部として自分があること。
それが、還虚の体験であり、「本当の自分を生きる」ための土台となるのです。
ユング心理学の道:個性化とヌミノース体験
── 心の奥で“神聖なるもの”に出会うとき
西洋心理学の巨匠カール・グスタフ・ユングは、人の心を「自我(Ego)」と「無意識(Unconscious)」という二つの層で捉えました。
私たちが“自分”だと思っている意識は、実は心のごく一部にすぎません。
その深層には、広大な無意識の領域があり、そこには個人の記憶を超えた“集合的無意識”が流れています。
ユングは、自己の深層との対話の結果おきる、自我と無意識の統合の過程を「個性化(Individuation)」と呼びました。
個性化 ― “全体としての自分”に還るプロセス
「個性化」とは、性格を磨いたり、成長を目指したり、特別な自分になることではありません。
心の中で分断されていたものが再びひとつに結び合う、内的統合の道です。
それは自分という存在を知り、深めていくことです。
私たちの中には、光と影、善と悪、理性と情動など、さまざまな相反するエネルギーが存在しています。それらは葛藤として人生の中で浮上してくるものです。
ユングはそれを「元型」と言う概念で説明しました。元型とは、人類が共有している普遍的な心のパターンのことで、集合意識(潜在意識レベル)に存在しているとされています。
それらを拒絶したり排除するのではなく、“ありのままに認め、見守る”ことによって、統合され、やがて内なる全体性(Self)が徐々に姿を現します。
ユングはこの自己(Self)を、心理的な中心であり、「神的元型」でもあると考えました。
曼荼羅や円で象徴されるものです。
個性化とは――外にある神ではなく、内に宿る聖性を思い出す道です。それは道家の「還虚」と同じく、“分離したものが大きなものとの統合へと帰るプロセス”なのです。
ヌミノース体験 ― 心の中に神が現れるとき
ユングが特に重視したのは、人が無意識の深みで“神聖なるもの”に出会う瞬間でした。
彼はそれを、神学者ルドルフ・オットーの言葉を借りて、「ヌミノース体験(numinous experience)」と呼びました。人間の深層に起こる宗教的・霊的体験です。
具体的には、
- 畏怖(awfulness)と魅惑(fascination)が同時に訪れる
- 自我では説明できない、超越的な力との遭遇
- 意志では起こせない、無意識からの圧倒的な働きかけ
- 体験者の内面が根底から変容する、魂の震え
として説明されています。そしてこれこそが大いなる自己(self)との邂逅です。
それは、恐れと魅惑が同時に訪れる体験――
自分を超えた何か大いなる存在が、心の中で“確かに生きている”と感じる瞬間です。
光に包まれるような感覚のこともあれば、深い闇に吸い込まれるような体験として訪れることもあります。
しかしどちらの場合も、その体験の後、人は同じ自分ではいられなくなる。
それほど、自我にとってはなす術のない抗いようのない体験であるとユングはとらえています。
“自我”の中心が静かにずれ、“自己(Self)”という大いなる中心へと置き換わっていく。
これが個性化で起きる統合のプロセスであり、これを繰り返して最後には自己という大いなる統合の場へと帰還します。
痛みと闇を通して目覚める「内なる神」
ユングは、心の苦しみや病理の中にも「自己(Self)の導き」が働いていると考えました。
抑圧された感情やトラウマ、夢に現れる象徴――それらはすべて、魂が「本来の姿」を思い出そうとする内なる神の神聖なメッセージなのです。
闇を避けず、その中に光を見出すことで、人は再び「全体の流れ」に戻っていく。
それは「本当の自分」から生じる氣の流れであり、自分が“全体の流れ”の中にあることを思い出す氣功の探究の道と共通しています。
苦しみを消すことではなく、苦しみとの関係を変えること。そこに心の調和と再統合が生まれるのです。
これが真の「癒し」です。
還虚と個性化 ― 「本当の自分」を生きる道
道家の修行者が「無為自然」に還るように、ユングの個性化もまた、「操作する自分」から「委ねる自分」への転換です。
それは、内丹術でいう「神が虚に還る」プロセスと心理的に同型の構造をもっています。
“私が生きる”という意識から、“生命が私を通して生きている”という気づきへ。
それが「本当の自分」とともに生きるということ。
還虚も個性化も、「本当の自分を思い出す」ための道なのです。
比較と統合:東西の“還る道”
── すべての道は「静けさ」へと続いている
東洋の「還虚」と、西洋の「個性化」。異なる体系のように見えますが、その深層には驚くほど似た構造があります。
どちらも、「分離していた自分が全体へと還る」プロセスであり、そこでは“自我”という限定がほどけ、より大きな生命の流れ──本当の自己──に包まれていきます。
道家の修行者は、「氣」を精錬し、“無”へと帰る中で宇宙と一体となる道を歩みました。
ユングは、人の心が“無意識の深み”へ降りていくことで、“自己(Self)”という聖なる全体へ目覚める道を示しました。
異なる言葉、異なる時代。
けれど、二つの道が照らしているのは同じ山の頂、──”「本当の自分」とともに一つにある場”。
いずれも、「自我」の限定性がほどけて、より大き生命の流れに還る道の先に辿り着くところです。
”私は私であり、同時に全体でもある”
”私を通して世界が息づいている”
こうした言葉で表現される感覚こそ、「本当の自分」を生きることであり、小さな自分を超越して生命の目的と一体となる生き方です。
還虚と個性化の構造的対応
ここで、東西の二つの体系を簡潔に整理してみましょう。
氣功・内丹術とユング心理学が、それぞれどのように“還るプロセス”を描いているか表にまとめてみました。
氣功・内丹術の「還虚」とユング心理学の「個性化・ヌミノース体験」の比較
| 観点 | 現代氣功・内丹術における「還虚」 | ユング心理学における「個性化・ヌミノース体験」 |
|---|---|---|
| 目的 | 「氣」の循環を通じて虚(空)に還り、天地人が一体となる“無為自然の境地”に至る。=真我(本当の自分)への帰還 | 自我と無意識を統合し、“自己(Self)”という全体性に目覚める。=個性化(Individuation)=自己実現 |
| 中心概念 | 無極 → 太極 → 陰陽 → 還虚(無に還る)内丹術では「返照」「守一」「虚静」 | 自我(Ego)と自己(Self)の統合。「シャドウ」「アニマ/アニムス」「自己」などの統合プロセス |
| プロセスの性質 | 精 → 氣 → 神 → 虚(還虚)というエネルギーの精錬と還元。“有”を超えて“無”に帰る内的錬成。 | 無意識の統合を通して自我が拡張・超越される。“部分的自己”が“全体的自己”へ統合される心理的錬金術。 |
| 体験の核心 | 「無我・無心」──天地と一体になる体験。“自己”という枠が溶ける。 | ヌミノース体験──神聖なるものに触れる“内的啓示”。 |
| 神聖性の位置づけ | 神は外にあるものではなく、自らの中にある氣=生命そのものの流れ。→ 内なる聖性の覚醒。 | 神的体験は“無意識の神性”との遭遇。→ 内的神体験(Inner God experience)。 |
| 癒し・変容の仕組み | 痛みや滞りを氣の流れとして観察し、静けさの中で統合。 | シャドウやトラウマを統合し、無意識エネルギーを再分配。 |
| 最終到達点 | 無為自然・還虚・玄(げん)──「氣が私を生かす」。 | 自己実現──「自己が私を通して生れのながえ |
解説:二つの道に流れる“同じ氣”
異なる表現でありながら、同じ意識の変容プロセスを指しています。
内丹や氣功で語られる「氣」は、ユングが言う「リビドー(心的エネルギー)」と同じく、生命そのものの流れです。
リビドーとは、もともとはフロイトが性的欲動として位置づけたものを、ユングが生命そのもののエネルギーとして発展解釈をしたものです。
彼の言うリビドー=心的エネルギーとは
- 創造性
- 精神的探求
- 無意識との対話
- 魂の統合への衝動
といった、魂の深層を動かす氣のような流れそのもの。
ユングは、易経を研究した異端の心理学者であり、「氣」や「陰陽」「還虚」といった概念に似たものを、心理学的な言葉で探求していたように思われます。
いずれにしても、氣やリビドーは、「虚空」や大いなる自己へとおのずと還る流れであり、これが滞れば心身が分離し、流れれば調和します。
鍵となるのは、外側に向いていた意識を内側に返すこと。
ユングはそれを、「自我が自己(Self)を見つめること」 と語り、 道家や氣の哲学は、 「観照によって、虚へと還ること」 を説いています。
ユングは夢や象徴を通して無意識を観照する道を模索し、東洋には呼吸と身体を通して氣の流れを観照する道があります。
現代に生きる私たちへ ─ 東西融合の時代における「氣」の探究
古い時代には、限られた教えや実践体系の中でしか氣や心の本質に触れることはできませんでした。
しかし現代に生きる私たちは、認知科学や量子論など最先端の科学の恩恵を受け、また東洋と西洋の叡智の双方に触れることができます。
それはつまり──
“氣”を、心と宇宙の両面から理解できる時代に生きているということ。
東西の古の叡智と、現代の知の光。
その両方を同時に学べるという事実こそ、現代人の魂の道を照らす新しい光なのです。
知識的な理解は実践を支え、実践は知識を生きた智慧へと昇華させます。
この相互循環の中で、私たちはかつてないほど身近に「真理」に触れることができるのです。
「氣」とは生命を動かす心のエネルギー
ユングがリビドー(心理的エネルギー)と呼んだもの。
それは、氣功でいう「氣」と本質的に同じものです。
「氣」とは、心のエネルギーであり、生命を動かす根源的な力。
だから、氣功を学び実践することは、単なる健康法ではなく、“生きることそのもの”を探究する道なのです。
三和氣功は、現代の恩恵を最大限に活用し、多面的なアプローチで「氣」を探求します。
科学的理解(認知科学・量子論・心理学)と、古の叡智(道家・仏教・内丹術の哲学)を両輪として、「感じる」「理解する」「生きる」を統合します。
知識は実践を深め、実践は知識を生きた智慧へと変える。
このプロセスの中で、私たちは「本当の自分」と出会い、その「本当の自分」と共に生きる道へと還っていくのです。
第5章 氣を感じることは魂を感じること
── 身体を通して「本当の自分」と出会う
氣を感じるということ。
それは、特別な感覚ではなく、誰もが本来もっている生命の記憶を思い出すことです。
静かに呼吸をし、身体の内側で何かが“流れている”ことに氣づく瞬間。
その流れは、血や神経よりも深く、意識が生まれるよりも先に働いているいのちのリズムです。
それを感じるとき、私たちは「私」という境界を越え、世界とつながっていることを思い出します。
感じるとは、観照すること
氣を感じるとは、「何かを感じようとすること」ではなく、すでに流れているものを“観る”ことです。
目を閉じ、呼吸の波をただ見守ってみてください。
吸うとき、胸がふくらみ、吐くとき、肩の力が抜ける。
その一連の流れの中に、あなたの意識を超えた“働き”があります。
氣功ではこの“働き”を自然智(じねんち)と呼びます。
それは、心臓を動かす力でもあり、傷を癒す力でもあり、また季節を巡らせ、星を運ぶ力でもある。
氣功の実践とは、この自然智が自分の中にも確かにあるということを学ぶこと。自分の意志で何かを“する”のではなく、すでに働いている“氣の流れ”に耳を澄ませることを学ぶのです。
それはあなたの中にある宇宙の知性。
氣を感じるとは、この自然智の導きを受け入れ、それと再び調和する行為なのです。
魂が身体を通して語りかけるとき
私たちはしばしば、「魂」は高い場所にあるもので通じがたいものであると認識しているかもしれません。
しかし、そうではありません。
魂はいつも身体を通して語りかけています。
痛み、呼吸、温かさ、涙──それらはすべて、魂が発する信号。
氣を感じるということは、その信号に耳を澄ませることでもあります。
そして、そこに抗わず、分析せず、解釈せず、寄り添うこと。
そのとき、私たちは魂、「本当の自分」とのつながりを思い出し始めます。氣が通いはじめ、内側には静けさが満ちていく。
その静けさこそ、「本当の自分」が棲む場所、“在る”という感覚なのです。
感じることが還ること
氣を感じることは、生命を感じること。
魂を感じること。そして宇宙を感じること。
内なる神を感じること。大いなる自己を感じること。
根源の虚空を感じること。
感じるとは、分離を越えて“ひとつ”に戻る行為です。
知識を超え、理論を超え、今この瞬間、呼吸とともに在るとき──あなたはすでに「還虚」の入口に立っています。
氣功とは、その入口に何度も立ち返る練習。
何度も感じ、何度も忘れ、何度も還る。
その繰り返しの中で、魂はやがて、自らの中心──本当の自分──を生き始めます。
第6章 病を超える意識 ― 弱さと影が光に還るとき
── 「治る」から「在る」へ
人が「本当の自分」に出会うとき、もはやそこには「病人である自分」や「弱者である自分」を存在させる必要がなくなります。
弱い自分、欠けた自分、罰を受けるべき自分。それらは“分離した自我”がつくり出した一時の仮面にすぎません。
“誰かに認めてもらうための自分”を生きている間は、心は絶えず緊張し、氣は外へ流れ続けます。
しかし、「本当の自分」を思い出すとき、私たちはその緊張の根を静かにほどいていきます。
「治す」とは、自己否定からの発想
現代社会では、病や不調を「治すべきもの」「正すべきもの」として扱います。
けれども氣功の視点では、“治そうとすること”の中に、すでに分離が生まれているのです。
治したい、変えたい、正したい。その根底には、「今の自分ではいけない」という否定があります。
けれど、ユングが示したように、魂のレベルで見ると病も苦しみもすべて“氣のメッセージ”。
つまり、「あなたが本来の場所に還るための導き」なのです。
氣の流れが滞るとき、そこには“生き方のズレ”=不自然が生じています。
しかし、その不自然に気づき、滞りを無理に取り除こうとせず、ただ観て、受け入れ、氣を通わせていく。
そのとき、滞りは自然に融け、「治る」というより、「調う(ととのう)」という現象が起こります。
癒しとは「自分がいなくなること」
ユングが言うように、「癒しとは苦しみを取り除くことではなく、 苦しみとの関係性を変えること」です。
さらに一歩進めて考えると癒しとは、“癒される自分”がいなくなること。
痛みも、恐れも、罪悪感も、ただ氣の流れとしてありのままに観えてくるとき、苦しんでいる“私”という限定的な存在は静かに溶けていきます。
残るのは、ただ生命の呼吸。
癒される自分もいなければ、癒してくれる誰かもいなくなります。
“誰が癒し、誰が癒されるのか”という二元を超えた、純粋な「在る」の場です。
ここに至って初めて、人は「治る」「変える」という概念そのものを手放します。
病を超えるとは、分離を超えること
病や苦しみが消えるのではなく、それを“悪”とする観点が消えていく。
その瞬間、身体も心も、もはや「敵」ではなく、 ずっとそばにいてくれた“友”として感じられる。「友」として感じられます。
緊張がほどけ、生命が再び流れ出す。
その自然な流れの中で、“生かされている”という感覚が甦るのです。
この意識の変化こそが、三和氣功が語る「存在の自由」。
それは、何かになるための努力ではなく、今ここに在ることを許す自由。
ありのままの自分が、すでに調和の中にあると知る自由です。
病という「人間の象徴」
病とは、単なる身体の異常ではなく、人間という存在が最も否定してきたものの象徴です。
それは、「弱さ」や「無力さ」、そして「死」や「終わり」といった、自我が恐れるすべてのものを映し出す鏡。
私たちは長い間、それらを“避けるべき影”として扱ってきました。
けれど、魂の視点から見れば、その影こそが、最も深い統合の扉なのです。
死も、苦しみも、消すべき敵ではなく、生命が自らの完全性を思い出すための象徴的体験。
そこに手を合わせ、受け入れたとき、人間は“有限の存在”を超えて“無限のいのち”とひとつになります。
在ることの中に光がある
だから、病を超えるとは、死を否定することでも、永遠の健康を追い求めることでもありません。
それは、「生きること」と「死ぬこと」、「光」と「影」、「癒し」と「痛み」を、ひとつのいのちとして受け入れること。
そうして初めて、人は“本当の自由”に触れるのです。
氣は静かに流れ、魂は微笑み、生と死の間に、深い安らぎが満ちていく。
それが――三和氣功の語る「本当の自分を生きる」ということ。
すなわち、すべてを包含する生命の光として在るということなのです。
第7章 創造主として生きる ― 無為自然の創造へ
── 「在ること」が世界を動かす
癒しと統合の道は、終わりではありません。それは、創造の始まりです。
「還虚」によって心は静まり、「個性化」によって内なる全体と再びつながるとき、人は「創る」という行為そのものの本質を思い出します。
創造とは、意図を操作することではなく、存在そのものが働くこと。
何かを“しよう”とする前に、すでに生命が流れ、その流れが自然に形を生み出していく。
それが、無為自然の創造です。
創造とは、氣の流れが形を結ぶこと
すべての現象は、「氣」の流れが形をとったもの。氣が滞れば停滞が生まれ、氣が流れれば現実は動き出します。
けれど、氣を「動かそう」「コントロールしよう」とすると、そこにはすぐに自我の意図が入り、不自然が生まれ、滞りを強めます。
本当の創造は、“動かそうとしない”ところから生まれます。
静けさに還り、内なる中心に氣が満ちたとき、生命は自然に外へと溢れ出し、その溢れが「現実」として展開していくのです。
氣功とは、自分の内側にある創造の循環を思い出すための練習、氣が天地とともに巡り、 身体の奥で静かに息づいている生命のリズムを感じることです。
また、それは、考えたり分析したり、評価したり解釈したりする意識を、「感じる」や「存在する」という意識に戻すための実践でもあります。
それは、頭から胸へ、胸から丹田へと、 意識の重心が静かに降りていく旅。 ユングが語った「自我から自己への統合」も、 この意識の転換と深く響き合っています。
「私が創る」から「創造が私を通して流れる」へ
「創造主として生きる」とは、自分の意志で現実を支配することではありません。
多くの実践者は「思考を現実化する」ことを目指し、マインドの力によってそれを可能にしようとします。
確かに、それも人間の意識の一つの働きです。
けれど、三和氣功が歩むのは、そのさらに奥――“本当の自分”、自分を越えた自分とともに生きる道。
それは、「創造が私を通して流れている」ことを許す生き方です。
“私”という個の意識が静まり、生命そのものの意志に調和するとき、創造は努力によってではなく、自然の流れとして起こります。
この意識の転換が起こると、行動はより自然になり、結果への執着がほどけ、氣は自由に流れ始めます。
すると不思議なことに――解放されるべきものは解放され、本当に必要な人・出来事・タイミングが自然と揃う。
それは奇跡ではなく、氣の法則です。
浄化と創造が同時に起こる。
何かを変えようとせずとも、氣が調えば、世界は自然に調っていくのです。
これこそが、道家が語った「無為自然」。
操作を超えた創造、宇宙の働きそのものなのです。
無為自然 ― 操作を超えた創造
「無為」とは、何もしないことではありません。意図を超えて、自然の働きに一致すること。
人が還虚の静けさに還り、その中心で氣を感じ、魂と調和するとき、意図は“個の欲望”から“宇宙の流れ”へと変わります。
それは、“願う”のではなく、“すでに在る”を感じる創造。
“叶えよう”とするのではなく、“流れに委ねる”創造。
このとき、人は「操作者」ではなく、「創造そのもの」として生き始めます。
結び ― すべては「在る」から始まる
三和氣功が伝えてきた道は、癒しの道であり、還る道であり、そして創造の道。
氣を感じることから始まり、魂と再び結ばれ、やがて「本当の自分」が世界を創る流れそのものになる。
それは特別な力ではなく、誰の中にもある“在る力”の目覚めです。
創造とは、在ること。
在るとは、静けさに満ちて生きること。
その静けさの中で、世界はあなたを通して、今日も新しく創造されています。
🔗 関連ページ
👉 [本当の自分を生きる氣功プログラム]
── 還る・感じる・創造する、「在る」からはじまる氣功の道。
👉 [氣功師養成講座]
── 東洋の智慧と科学を統合し、「本当の自分」を生きるための氣功を学ぶ。
氣功師・ヒーラー
中国の伝統氣功と認知科学の知見をもとに、無理をせず、自然な流れに還るための氣功とヒーリングを伝えている。三和氣功が大切にしているのは、何かを変えたり、足したりすることではなく、本来の自分に還ること。
頑張ることを手放し、ありのままの状態に戻ったとき、
人はもともと備わっている力や調和を自然と思い出していく。
氣功を人生を操作するための方法ではなく、自然体で生きるための智慧として提案している。